~3つの遺言の特徴とポイントをわかりやすく解説~
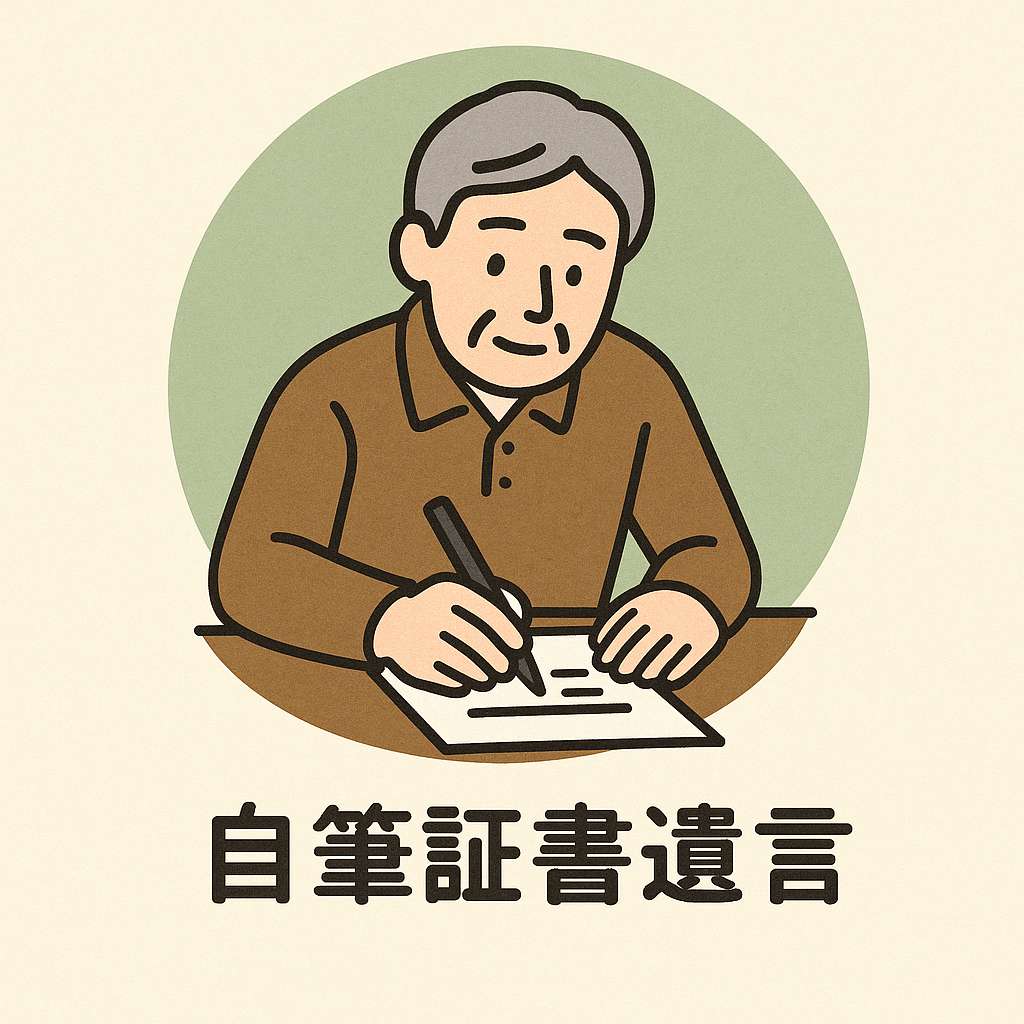
みなさんは、「遺言書(ゆいごんしょ)」と聞いて、どんなものを思い浮かべますか?
テレビドラマの中で、亡くなった方の書いた手紙のようなものを読んで「全財産は◯◯に…」といった場面を見たことがあるかもしれません。でも実際の遺言には、きちんとしたルールがあって、それを守らないと無効になってしまうこともあるんです。
今回は、一般の方がよく使う「普通方式の遺言」3種類について、それぞれの特徴や注意点をわかりやすくご紹介します。
1.自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
どんな遺言?
自筆証書遺言は、その名のとおり「本人が自分で全文を手書きして作る遺言」です。紙とペンがあれば誰でも簡単に書ける、もっとも身近な遺言の形です。
書き方のルール(民法第968条)
- 本文、日付、氏名をすべて手書きで書きます。
- 押印(はんこ)も必要です。認印でもOK
- 財産目録(不動産の登記簿や預金口座の一覧など)はパソコンやコピーでもOKですが、そのページには署名と押印が必要です。
(両面コピーの場合には両面に署名と押印が必要) - 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する
書き間違った場合の変更・追加
- 遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
注意ポイント!
- 書き方を間違えると「無効」になることがあります。
- 書いた遺言書が相続人に見つけてもらえないと、せっかくの想いが届きません。
- 相続開始後、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です。
でも安心!「法務局保管制度」があります
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度がスタートしました。これを使うと、検認が不要になり、紛失や改ざんの心配もなくなります。
2.公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
どんな遺言?
公証人という法律の専門家に内容を伝えて、書類にしてもらう遺言です。本人が話した内容を公証人が文書にまとめてくれるので、ミスがなく安心です。
作成の方法(民法第969条)
- 遺言者が2人以上の証人の前で口頭で内容を伝えます。
- 公証人がそれを文書にし、本人と証人が署名・押印します。
- 公証役場で手続きを行います。
メリット
- 法的にもっとも信頼性が高く、無効になる心配がほぼありません。
- 相続のときに検認がいらないので、すぐに使えます。
- 原本は公証役場で保管されるため、なくしたり改ざんされたりすることもありません。
デメリット
- 手数料がかかります(財産の額によって数万円〜)。
- 証人が2人必要で、内容を知られる可能性があります(ただし、専門家に依頼して証人になってもらうことも可能です)。
3.秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
どんな遺言?
内容を誰にも見せたくない人向けの遺言です。自分で遺言書を作り、封筒に入れて封をしてから、公証人と証人に提出します。
作成の方法(民法第970条)
- 本人が遺言書を作って封筒に入れて封印します。
- 公証人と証人2人の前に持って行き、「これは遺言書です」と伝えます。
- 公証人が、確かに本人が提出したという証書を作成します。
メリット
- 内容を誰にも知られずに、遺言書の存在だけ証明できます。
デメリット
- 本文は自分で作成するため、書き方に誤りがあると無効になるおそれがあります。
- 相続時には検認が必要です。
- あまり利用されておらず、手続きが複雑なこともあります。

それぞれの遺言には、メリットとデメリットがあります。
「費用をかけたくないから自筆証書遺言がいい」と考える方も多いですが、形式のミスで無効になってしまったり、相続人に見つけてもらえなかったりすることも…。
逆に、費用がかかっても確実に想いを伝えたい方には、公正証書遺言がおすすめです。
